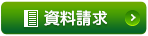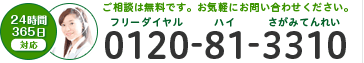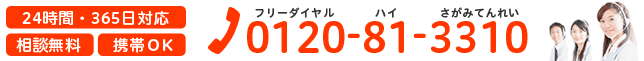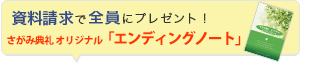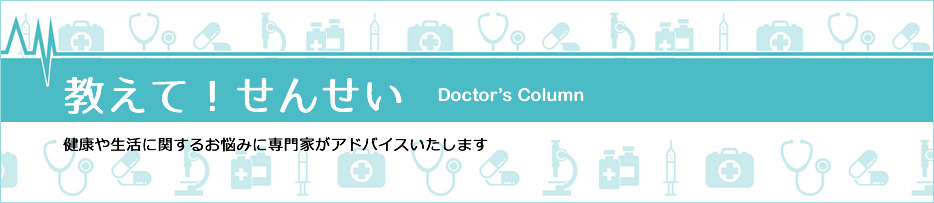

TEL.048-723-3333
大切な人を亡くした方に、つい励ましの言葉をかけてしまったことはありませんか?それは時としてその方をつらい気持ちにさせます。ご遺族を前にした時、私たちはどのような対応をすればよいのでしょうか。
心や身体の不調は自然な反応
誰しも身近な人の死を経験することがあります。特に配偶者の死は、その人の人生の中で最も強いストレスをもたらすといわれています。また、親や子どもなど肉親の死も相当なストレスになります。
ただ、亡くなった当初は、手続きなどに追われ、ストレスに起因する反応は少ないものです。しかし、諸々の手続きがある程度整理できたとき、ふと、気分が沈んでいる自分の状態に気づくことがあります。精神的な不調が進むと起こりがちなのが睡眠障害。さらに物事に取り組む意欲や集中力の低下。人によって違いはありますが、心身ともにさまざまな変化が起こってきます。こうした変化は、深くて辛い悲しみから自分自身を守るために起こる自然な反応です。
無理に声をかけず「寄り添う」こと
不調が長引いて社会生活に支障をきたすようになると、何かしらの精神保健的なケアが必要になる方もいます。そんなご遺族に向き合ったとき、私たちはかける言葉が見つからず微妙な間に耐えられなくなったり、何か言わなければ人間性を問われるのではないかと不安になったりしてつい、世間でよく使われているあたりさわりのない言葉をかけてしまいます。しかし、それはご遺族にとっては、まだ処理されていない心の課題を土足で踏みにじられるような行為であるかもしれないのです。
ご遺族との接し方は、基本的には「寄り添う」こと。無理に言葉をかける必要はありません。ご遺族が悲しみとともに歩き出せるようになる日まで、自ら語り始めるのをゆっくり待ちながら、そばで温かく見守ってあげましょう。

こんな言葉、ついかけていませんか? ご遺族をつらい気持ちにさせる「励ましの言葉」
□「○○さん、大往生だね」
(ご遺族がそう感じてこそ、はじめて大往生なのです)
□「残ったあなたが、がんばらなければダメだよ」
(心底疲れているご遺族は、がんばれません)
□「あなたの気持ちは、とてもよくわかります」
(本当にご遺族のことをわかっているのでしょうか)
□「まだ悲しんでいるの、早く元気になりなよ」
(悲しみから立ち直るまでには時間がかかります)